- はじめに:話す時間が増えたという“大きな変化”
- 夫婦間ミーティング:3カ月に一度の“現在地確認”
- 役割とルール:運用は私、見える化は二人で
- タイムホライズン別ビジョン:1年→3年→5年→10年→20年
- 会話を続けるための工夫:感情も“数値化”する
- おわりに:同じ地図を持つということ
- 2021年からの投資スタンス:貯蓄→投資へのシフト
- 情勢が荒い時期ほど“見える化”を強く
- ジュニアNISAも含めた“全体像”の共有
- 話し合いが“次の一手”を連れてくる
- 長期の視点がもたらす“遠い明るさ”
- 在宅ワークの“透明性”と、家の安心感
- 夫婦間ミーティングを続ける理由
- “ためる”と“使う”——価値を引き出す難しさ
- まずは“サウナ小屋”計画から
はじめに:話す時間が増えたという“大きな変化”
FIREしてから、妻と話す時間が目に見えて増えた。食事中の何気ない一言、子どもが寝静まった後の小さな会話、休日の車内での雑談——どれも短いが、積み重なると確かな流れになる。子どもの話が中心なのは我が家も同じだが、最近は「数年先」だけでなく「5年、10年、20年後」を視野に入れた対話が自然と増えてきた。
夫婦間ミーティング:3カ月に一度の“現在地確認”
その背景にあるのが、意識的に続けている「夫婦間ミーティング」だ。内容はシンプルで、3カ月に一度、お互いの資金管理状況を共有するだけ。とはいえ、やるとやらないでは大違いで、家計の“今”と“次”が立体的に見えるようになった。
進め方(我が家の型)
- 1. 現状報告:口座残高と投資評価額、直近3カ月の収支(固定費/変動費)
- 2. 変化点:予定外の出費・臨時収入・サブスク増減など
- 3. 小さな改善:固定費の1項目だけ見直す/翌四半期に試すことを1つ
- 4. 心のメモ:不安・期待・迷っていることを短く共有
役割とルール:運用は私、見える化は二人で
我が家は、メインの資産運用は私が担い、妻も別口座で積立を続ける“並走型”。
ルールは3つだけ決めている。
- 可視化:家族資産のダッシュボードを同じ画面で見られること
- 独立性:お小遣い口座と趣味口座は各自で自由裁量
- 安全網:生活費6カ月分の現金はタッチしない(非常用)
タイムホライズン別ビジョン:1年→3年→5年→10年→20年
“いつか”は動かない。そこで、期間ごとに目的→数値→行動の順に並べている。
1年先(次の四半期×4)
- 目的:家計の基礎体力を整える
- 数値:月次黒字を◯万円、貯蓄率◯%、固定費を◯%圧縮
- 行動:保険/通信/電力の1項目だけ見直し、教育費の積立枠を固定、旅行は年1回の枠で計画
3年先(生活の型を固める)
- 目的:教育・住まい・働き方の“我が家の標準”を決める
- 数値:リスク資産比率◯%、キャッシュバッファ6〜12カ月維持、年1回の家族プロジェクト
- 行動:子どもの習い事は上限枠内で入替制/車・家電の更新サイクルを明文化
5年先(選択肢を増やす)
- 目的:住み替え・教育進路・働き方の“選べる余白”を確保
- 数値:家族資産◯◯◯◯万円、学資口座◯年分先取り
- 行動:居住エリアの候補地を年1回視察/副収入の柱を1→2本へ
10年先(家族のステージ移行に備える)
- 目的:子の進路分岐と親の健康投資を同時に進める
- 数値:医療・介護の備え枠を設定、資産配分のリバランス基準を文書化
- 行動:親の健康スクリーニングを年次ルーチン化、学費山を“積立+現金”で平準化
20年先(“続ける暮らし”をデザイン)
- 目的:子が独立しても“夫婦で回る日常”を用意
- 数値:生活コストの把握(ミニマム/スタンダード/ご褒美月)
- 行動:地域・趣味・学びのコミュニティを3本持つ/住まいのダウンサイジング可否を検討
会話を続けるための工夫:感情も“数値化”する
数字は進捗を示すが、感情がついてこないと続かない。そこでミーティングの最後に、互いの気持ちを0〜5の主観スコアで共有している。
- 不安度/安心度/ワクワク度/負担感(各0〜5)
- 次の3カ月で「増やしたい感情」「減らしたい負担」を1つずつ言語化
おわりに:同じ地図を持つということ
資産運用は私がメイン、でも地図は二人で持つ。3カ月に一度のミーティングは、数字を合わせる場であると同時に、価値観のピントを合わせる時間でもある。
1年先の小さな達成感が、3年先の安心感をつくり、5年・10年・20年で「この暮らしを続けていきたい」という確信に変わっていく。話す時間が増えた今だからこそ、無理なく続けられる“我が家の型”を、これからも少しずつ育てていきたい。
2021年からの投資スタンス:貯蓄→投資へのシフト
我が家は2021年から、資金を段階的に貯蓄から投資へと移し替えてきた。初期は短期売買も試したが、いまは大きな資金は基本ホールド。時間を味方につける方針に落ち着き、少しずつだが確実に増やせている。
情勢が荒い時期ほど“見える化”を強く
ここ最近は、国内外の政治・安全保障・景気動向などが揺れやすく、相場のボラティリティも大きい。そこで、四半期に一度お互いの資金状況を並べて確認する習慣を導入。価格の上下に引っ張られるのではなく、全体像と進捗で意思決定するためだ。
ジュニアNISAも含めた“全体像”の共有
子どものジュニアNISAなど口座が複数あると、確認項目は正直増える。それでも、家族資産のマップが描けると、過去から積み上げてきたものが形になりつつある実感に変わる。これは、私にも妻にも大きな安心材料だ。
話し合いが“次の一手”を連れてくる
現状がクリアになると、自然と会話が前向きになる。「今は何をすべきか」「次の3カ月で何を試すか」。サイドFIREで積立額は当初より下がったが、いまも毎月5万円以上は継続中。さらに5〜10年後の計画——たとえば「小さなサウナ小屋」や「アトリエ」といった具体的な夢——に向けて、積立を増やすための工夫(固定費の微調整・副収入の柱づくりなど)も会話に自然と上るようになった。
長期の視点がもたらす“遠い明るさ”
「10年、20年と売らずに持ち続けたらどのくらいに育つのか」。ざっくりでも見通しが描けると、遠い未来の話が現実の選択肢として語れるようになる。数式の正確さより、夫婦で同じスケールで物事を見られることのほうが大切だと感じている。
在宅ワークの“透明性”と、家の安心感
私は平日、家で作業する時間が長い。だからこそ、ときどき「この人、昼間に何しているんだろう」と思われていないかな、と気にする自分もいる。四半期ミーティングで状況を可視化して共有しておくのは、私にとっても妻にとっても、ささやかな安心の土台だ。
夫婦間ミーティングを続ける理由
この小さなミーティングは、これからも定期的に続けたい。FIREを目指す家庭は往々にして資産の最大化に意識が向きやすい。将来を思索するのは価値がある一方で、一緒に生きる相手の感情に配慮し、その満足を損なわない設計も同じくらい大切だと思う。
“ためる”と“使う”——価値を引き出す難しさ
先達の言葉どおり、ためることと同時に、使って価値を引き出すことは難しい。けれど、他人の物差しに振り回されず、自分たちの欲求と家族の満足を丁寧に言葉にできれば、少しずつ上手にできるはずだ。必要なもの、満たされることを、何度でもすり合わせていく。
まずは“サウナ小屋”計画から
というわけで、まずはサウナ小屋のために、またコツコツ貯めていく。自作ならコストを落とせるのか、どの素材が現実的か——そんな話を妻とする時間も、すでに楽しい。小さな夢を地図に書き込み、四半期ごとに1マスずつ色を塗っていく。そんな歩き方を、これからも続けていきたい。

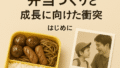

コメント