正直に言えば、僕は「どうしてもやりたくて仕方がない!」と胸が燃えるタイプではない。学生時代から今に至るまで、強い衝動よりも“ご縁”や“流れ”で物事を始めてきた。けれどそんな僕にも、いつの間にか身体の一部になったものがある。20年以上続けているスポーツだ。始まりは、友人に誘われての半ば“いやいや”。それでも気づけば、週末にその予定がないとソワソワする自分がいる。
じゃあ、なぜ続いたのか。技術の向上や試合の高揚感よりも、僕をここまで連れてきたのは“人”だったと今ははっきり言える。同じ汗をかき、励まし合い、時にぶつかり、また笑い合える仲間の存在。プレーが上達したから友達ができたのではなく、友達がいたから続けられた。続けることが特別なのではなく、続けられる環境が特別だったのだ。
その気づきは、これからの時間の使い方を変えた。僕は30代後半でサイドFIREを選び、子どもや自分のための可処分時間がぐっと増えた。多くの人が定年や60歳を迎えてから「やりたいこと」を始めるなら、僕には20年ほど早い助走期間がある。この贈り物みたいな時間を、ひとりの消費ではなく“関係”を育てる投資にしたい。
だから、趣味を増やす。音楽、釣り、登山、DIY、料理——どれもプロを目指すわけじゃない。うまくなくていい、速くなくていい。ただ“続けられる仕組み”と“誘える仲間”を増やす。目標はシンプルだ。平日の夜、なかなか会えない友人に「この趣味、おもしろいぜ。今度いっしょにやろう」と気軽に言える自分であること。
仕組み化のコツは三つある。ひとつ、初期ハードルを徹底的に下げること(道具はレンタル、場所は近所、時間は60分以内)。ふたつ、記録ではなく“約束”を残すこと(次回の日時をその場で仮押さえ)。みっつ、できた・できないの評価をしないこと(続いたら成功、止まったら再開が正解)。この三つを守ると、「熱量がないから続かない」ではなく「熱量がなくても続けられる」に変わる。
もうひとつ、大切にしたいことがある。子どもに“挑戦の背中”を見せることだ。新しいことは最初うまくいかない。それを大人が笑って受け止め、工夫して少し上手くなる姿は、どんな言葉より強いメッセージになる。「できない」は恥ではなく、次の「できた」の前段階。心が動く瞬間は、年齢に関係なく最高に楽しい——その事実を、日々の小さな挑戦で共有したい。
具体的には、シーズン制で回す。春は登山の入門コース、夏は早朝の釣り、秋はDIYで小さな棚づくり、冬はスープを極める料理。音楽は一年を通して週1回、15分の“音出し”だけ。どの趣味も、初期投資はミニマム、移動は最短、同伴は歓迎。上達のベクトルよりも、継続のリズムを優先する。カレンダーに「友だちと」「家族と」「ひとりで」の三色マークをつけて、偏りを見える化するのも楽しい。
もちろん、空回りする日もある。雨で山が中止になり、釣果ゼロで帰る日もある。包丁の角度が安定せず、スープがぼんやりする夜もある。それでいい。むしろ“想定外”があるから、次の一手を考える余白が生まれる。続けるとは、うまくいかなかった自分を諦めず、次の自分に譲渡する営みだ。
長く続けたスポーツが教えてくれたのは、「情熱は後から育つ」ということだった。最初から燃えている人もいるけれど、多くの人にとって情熱は“続けた先で静かに点火する”。僕はその点火を、これからの趣味で何度でも味わいたい。そして、その火を友人や家族と分け合いたい。誘える場所と、誘える時間と、誘える心の余裕を持って。
20年早い助走は、結果を急がない贅沢でもある。うまくなろうとするより、好きでい続けられる環境をつくる。勝とうとするより、また会いたくなる関係を育てる。今日、道具を買いそろえる必要はない。まずは一歩、小さく始める。週末にスープの材料をひとつ変える。近所の里山に30分だけ登ってみる。古いギターの弦を張り替える。そうやって増やした“小さな好き”が、やがて僕のアイデンティティの輪郭をやさしく太くしていく。
いつか、平日の夜にメッセージを送ろう。「この趣味、おもしろいぜ。いっしょにやろう。」その言葉が自然に出てくる自分でいたい。子どもたちにも同じ背中を見せたい。大人も子どもも、心が動く瞬間はやっぱり楽しい。だから僕は、今日も小さく始め、また明日も小さく続ける。
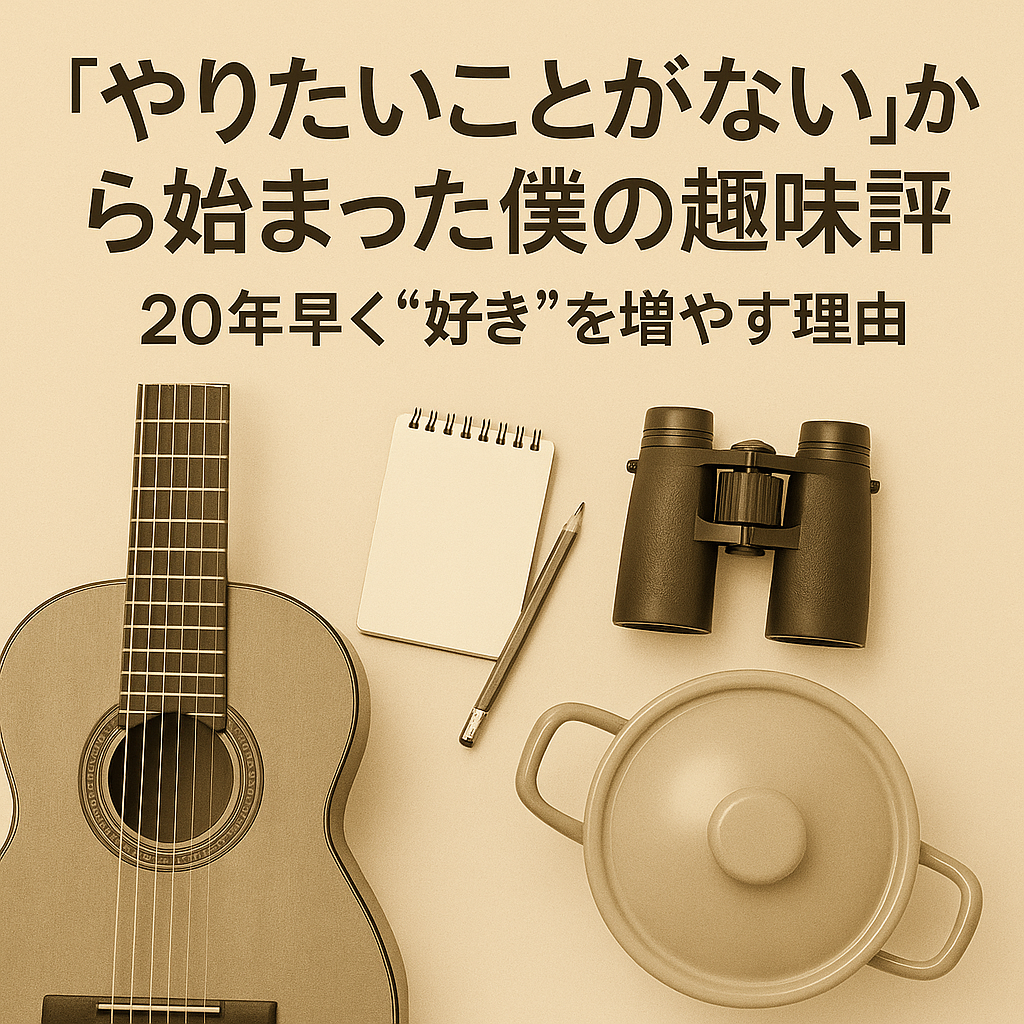
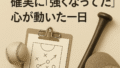
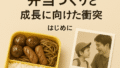
コメント