この記事は約4分で読めます
先日、以前から趣味のスポーツで指導していた子どもたちの試合を観戦した。チームスポーツは一人で勝てるものではない。それでも、この日は特に、長く見てきた一人の選手がグラウンド全体の空気を変えていた。プレー中の視線の配り方、味方への声かけ、ボールがない局面での一歩目。そのどれもが、彼の“持ち味”を最大限に発揮していて、試合を静かに動かしていた。
結果だけを言えば、1点差の惜敗だ。スコアボードには悔しさしか残らない。しかし、内容は違う。身体的に有利とは言い難い彼が、そのハンディを感じさせない走りと判断で、互角以上の勝負に持ち込んでいた。数字には映らない“効いているプレー”が、確かにそこにあった。
思い返すと、ここに至るまでの時間を僕は知っている。ボールを使わない地味な反復練習、うまくいかない練習試合、短い集中が切れて表情が曇る瞬間。そこから、また前を向いて小さくやり直す背中。指導者として隣に立ってきたからこそ、今日の“当たり前に見える好プレー”が、いかに脆く、そして尊い積み重ねの上に立っているかを知っている。だからこそ、自分の試合以上に、胸が熱くなった。
勝てなかった。けれど、勝つために必要なピースが、いくつも現れていた。試合後のベンチで、彼らの目は悔しさと同じくらいの手応えで光っていた。「次はこの場面でこう投げよう」「試合中フォームがブレたときの落ち着き方を一つ増やそう」——そんな言葉が、自然に口から出てくる。負けを“材料”として飲み込み、次の一歩を自分の言葉で決められるようになっている。これは強い。
僕自身もまた、彼らに感化された。向上心は、いつでも大きな炎である必要はない。むしろ、日々を照らす小さな灯りでいい。練習メニューを一つ増やすことより、続けられるメニューを一つ濃くすること。派手な改善より、ミスを一つ減らすこと。積み上げた先にある景色は、ある日突然に訪れるのではなく、いつの間にか“できてしまっている自分”として現れる。
今回、特に印象に残ったのは「持ち味を生かし切る」という姿勢だ。身体的なアドバンテージが少ないなら、正確さと、相手の裏をかく読みで補うこと。スピードで劣る分は、コントロールとタイミングで埋める。得点という分かりやすい成果だけではなく、相手をよく研究した苦手を突く配球、相手に迷いを生むプレッシャー、審判に伝わるクリーンさ。そうした“見えづらい勝ち筋”を、彼は自分の武器にできていた。これは、練習の中で何度も失敗し、選び直してきた証拠だ。
スポーツの良さは、勝敗がはっきりするところにある。ただし、勝敗は“最後に出る結果”であって“途中の評価”ではない。今日の彼らは、途中の評価で明らかに勝っていた。集中の濃度、声の届き方、リカバリーの速さ。喉まで出かかった歓喜の代わりに、静かな確信だけが残る。次に、勝ちに行ける。そう思えるチームになっていた。
指導者の役割は、技術を教えることだけではない。成長の速度が落ちた時に、焦りではなく観察を差し出すこと。うまくいかない日が続く時に、量ではなく順序を整えること。そして、勝てなかった日の帰り道に、言葉を詰め込まず、悔しさと手応えの両方を持ち帰らせること。今回、僕は逆に教えられた。彼らはもう、自分たちで前に進む燃料を作れるようになっている。
では、明日から僕は何をするか。まず、自分の練習にも“持ち味の定義”をもう一度書く。何で勝ち、どこで負け、何を減らし、何を増やすのか。次に、試合終盤の判断を想定したミニゲームを1本だけ増やす。量ではなく、質を一点濃くする。そして最後に、今日の感動を短く残す。心が動いた時にだけ見える筋道は、数日後には薄れてしまうからだ。
悔しさと誇らしさが同居する、あの独特の空気。勝てなかったのに、心のどこかが満たされている。あの子たちがもう一歩踏み出す日、今日の1点差は、きっと必要な距離だったのだと思う。次は勝とう。けれど、今日のこの一歩も、確かに勝ちだった。僕はそう信じている。
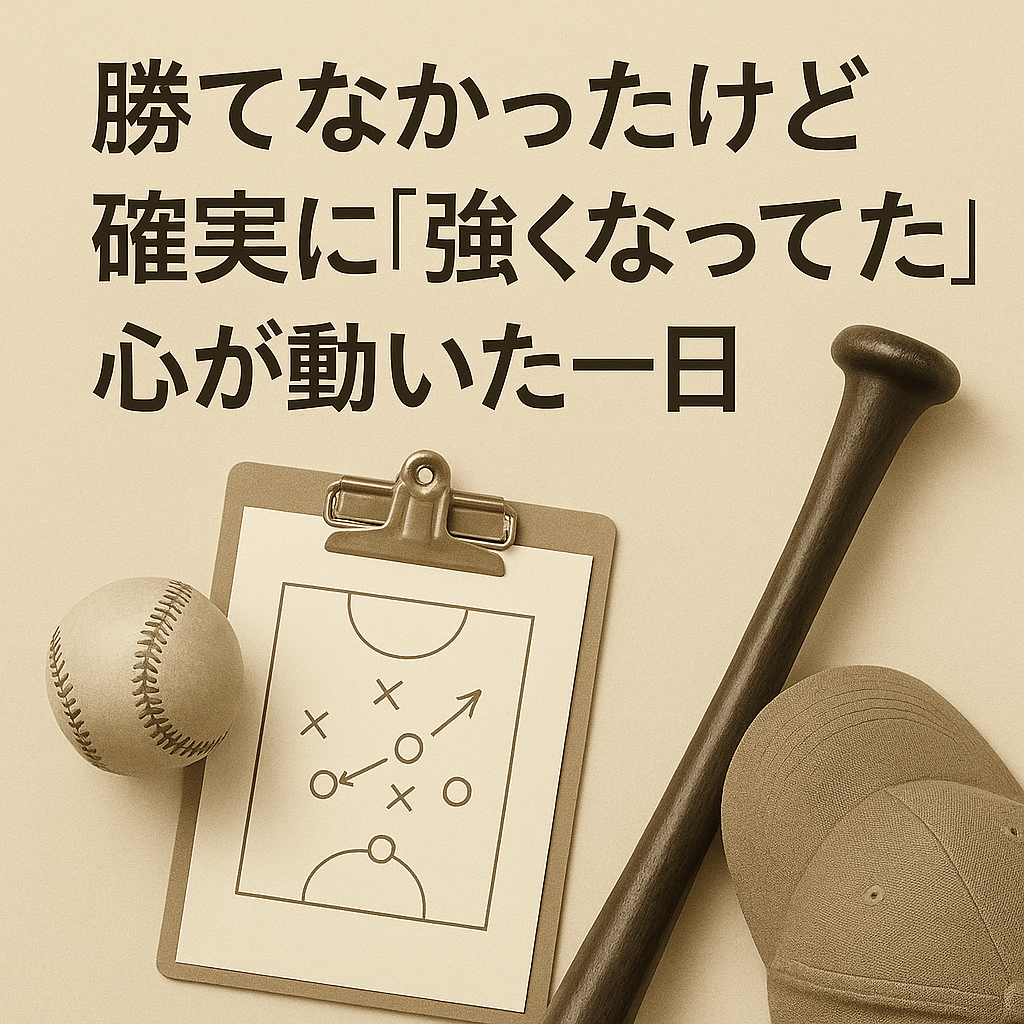
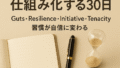
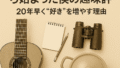
コメント